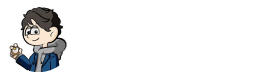飲食店を経営する上で避けて通れないのが「原価率」の問題です。売上をいかに伸ばすかと同じくらい重要なのが、「利益をどう残すか」。その鍵を握るのが、日々の仕入れと原価管理です。
今回は、飲食業における原価率の基本から、業態別の目安、リスク管理の視点、そして開業準備時に気をつけたいポイントまで、5つの視点で詳しく解説します。
1. 原価率とは何か?なぜ重要なのか?
「原価率」とは、売上に対してどれだけの金額を食材費に使っているかを示す指標です。
計算式はシンプルで、原価 ÷ 売上 × 100(%)。
たとえば、月商100万円の店で食材費が30万円なら、原価率は30%ということになります。
この数字を把握していないと、どれだけ売上があっても「気付けば利益ゼロ」という事態に陥りかねません。
利益=売上−経費(原価+人件費+その他)。
この構造を意識しなければ、経営の安定はあり得ません。
2. 業態別の原価率目安を知る
原価率の「理想値」は、実はお店の業態によって大きく異なります。
以下はあくまで目安ですが、開業前や改善の参考になります。
-
✅ 居酒屋:30%前後
→ 幅広いメニューと適度な価格帯で、原価のバランスが取りやすい業態。 -
✅ ラーメン店:25%前後
→ 主力商品が決まっており、食材構成もシンプルなため原価管理がしやすい。 -
✅ 高級レストラン:35%以上も可
→ 高級食材や丁寧な調理を売りにするため、原価が高くても価格転嫁しやすい。
つまり、「この原価率が理想」と一律には言えず、業態・コンセプト・客単価に応じた設定が必要になるのです。
3. 原価率が低すぎるリスクにも注意
「原価率が低い=経営がうまくいっている」と考える方も多いですが、これは必ずしも正解ではありません。
確かに、原価率が低ければその分利益は出やすくなります。しかし、食材の質を落とす・ポーションを減らすなどの原価削減を繰り返すと、料理の満足度が下がり、顧客離れにつながるリスクがあります。
実際、「最近味が落ちた」と感じられただけで、リピーターを失うことも。
利益と品質のバランスを保つことが長期的な経営には不可欠です。
大切なのは「数字だけ」で判断せず、自店の価値提供を守りつつ利益を残せる水準を見極めることです。
4. メニュー構成と仕入れ戦略がカギ
原価率の適正化には、日々の仕入れやメニュー設計の工夫が大きく影響します。たとえば:
-
仕入れ先を複数比較し、価格・鮮度・納期を最適化
-
ロスが出やすい食材を使い切る工夫(仕込みの活用・日替わりで使うなど)
-
高原価メニューと低原価メニューをバランスよく配置して全体の原価率を調整
-
メニュー数を絞って仕入れを効率化・管理を簡素化
特に、**「看板メニューはやや高原価でもOK」「サイドメニューで原価を下げる」**など、戦略的なメニュー設計は原価率改善に大きく貢献します。
5. 開業前から「適正原価率」の意識を持つ
これから飲食店を開業しようとする方にとっても、原価率は無視できないテーマです。
初期段階でのメニュー設計・仕入れルート選定・価格設定は、すべて「原価率」に直結します。
たとえば、こだわり食材を使いたい場合でも、それを活かす客単価・回転率・オペレーションとのバランスが取れていなければ、経営が立ちゆかなくなります。
また、創業計画書や融資申請においても、原価率をどう管理するかは評価ポイントの一つ。
開業前から「売価=仕入れ×〇〇%」と逆算する習慣をつけておくことで、現実的な利益設計が可能になります。
まとめ|原価率は「経営の体温計」
原価率は、飲食店の経営状態を表す“体温計”のようなもの。
高すぎても、低すぎても経営は不安定になります。
重要なのは、自店の業態やコンセプトに合わせて**“最適なバランス”を見つけること**。そして、数字に基づいて改善のPDCAを回すことです。
日々の仕入れ、メニュー設計、オペレーションを「感覚」だけで進めるのではなく、数字で可視化し、判断・改善していくことで、利益体質の経営が実現できます。
原価率の見直しは、明日からでも始められる“最も効果的な利益改善施策”のひとつです。
まずは、今月の原価率を計算してみることから始めてみましょう。