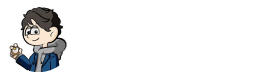飲食店経営において、どれだけ売上が上がっていても「資金繰りが厳しい…」という状況は決して珍しくありません。
日々の仕入れ、家賃、人件費…。固定費は容赦なく発生し、少しでも売上が落ち込めば、たちまち現金が不足します。今回は、飲食店の経営者が知っておくべき資金繰り対策を5つの視点から解説します。
① 運転資金は最低3〜6ヶ月分を確保せよ
飲食店は、季節や天候、イベントなどの影響を大きく受ける業態です。特に個人経営の飲食店では、予期せぬ売上減少が経営を直撃することも。
そこで重要なのが「運転資金の備え」です。
目安として、最低でも月の運営費の3ヶ月分(できれば6ヶ月分)の現金を手元に確保しておくことが望ましいとされています。
たとえば、毎月の経費が100万円かかる店舗なら、300万円〜600万円の資金確保が理想的。
この余裕があるだけで、突発的な売上減少にも冷静に対応できるようになります。
② 固定費は売上に関係なく発生する
資金繰りが苦しくなる最大の原因は、「固定費」です。売上がどれだけ落ち込んでも、家賃やスタッフの給料、水道光熱費は毎月必ず発生します。
つまり、売上が不安定な飲食店にとって、固定費のコントロールが資金繰り改善のカギとなります。
-
店舗規模や立地に対して家賃が高すぎないか?
-
スタッフのシフトは売上に見合った編成か?
-
電気代やガス代など、無駄な支出はないか?
これらを一度冷静に見直すことで、支出の圧縮が可能になります。
③ 融資制度を積極的に活用しよう
「手元に資金がない」と感じたら、早めに資金調達の検討を始めましょう。
おすすめは、次のような公的な融資制度です。
■ 日本政策金融公庫の創業融資
個人飲食店にも利用されている制度で、創業時・運転資金どちらにも対応。
比較的審査が通りやすく、返済期間も長いため資金繰りに余裕を持たせやすいのが特徴です。
■ 地銀・信用金庫の制度融資
地元に根付いた金融機関が独自に用意している制度融資。信用や実績があれば、有利な条件で借りられることもあります。
■ 自治体の制度融資
都道府県や市区町村が支援する低金利融資制度もあり、申請サポートも受けられます。
※どれも利益が出ているうちに申請するのが鉄則。資金ショートしてからでは審査が通りづらくなります。
④ 売上と経費の「見える化」を習慣に
資金繰りの悪化に気付いた時にはすでに手遅れ…というケースもあります。
そうならないために有効なのが、「資金繰り表」や「収支計画書」の作成です。
特におすすめしたいのは、週単位・月単位での現金収支管理です。
-
いつどの請求がくるか
-
どのタイミングで入金があるか
-
どの月に一番支出が多いか
こうしたことを一目で把握できるだけでも、資金不足への「予防策」が打てるようになります。
また、予実(予算 vs 実績)管理を行えば、どの費目が予定以上にかかっているのかも明確になり、早期対応につながります。
⑤ 小さな見直しが大きな改善に繋がる
資金繰り改善というと、「売上を増やす」ことばかりに目が向きがちです。
しかし、日常業務の小さな改善の積み重ねが、実は最も現実的で効果的な対策です。
たとえば…
-
食材の仕入れを週3回に分けてロスを削減
-
アルバイトのシフトを売上予測に合わせて調整
-
余剰在庫を持たないようにメニュー数を絞る
こうした小さな積み重ねが、1ヶ月後、3ヶ月後に確実にキャッシュ残高の差となって現れます。
まとめ:資金繰り対策は「早め」が鍵
飲食店経営において、「売上がある=安心」ではありません。
現金が足りなくなってからでは、打てる手は限られます。
だからこそ、資金繰り表の作成・固定費の見直し・融資制度の活用といった対策を、
“余裕がある今”から始めることがとても重要なのです。
資金繰りに不安を感じたら、ぜひ一度ご相談ください。
経営の数字に強い税理士として、御社の経営を数字面からしっかり支えます。