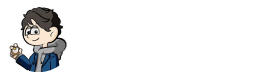「そろそろ法人化した方がいいのかな?」
個人事業主として事業を続けていると、一度は頭をよぎる悩みではないでしょうか。
-
利益は出ているけど、法人化すべきか分からない
-
法人設立の手続きが大変そうで後回しにしている
-
法人化のメリットやデメリットがよく分からない
実は、法人化には 判断基準 があります。
適切なタイミングを逃すと、余計な税負担やコスト増につながることもあるため注意が必要です。
本記事では、税理士として数多くの法人化相談を受けてきた経験から、「法人化すべき3つのサイン」 を詳しく解説します。
サイン① 年間所得が800万円を超えたとき
最も分かりやすい法人化の目安が個人「年間事業所得金額」です。
個人事業主と法人の税率の違い
-
個人事業主
所得税:5%~45%
住民税:一律10%
事業税:(所得-290万円)×5% -
法人
法人税率:約23%~33%(所得に応じて)
個人事業主は所得が増えるほど税率が上がる「超過累進税率」が適用されます。
そのため、一定以上の所得になると法人税よりも個人の所得税の方が負担が大きくなってしまいます。
具体的な比較
ここでは、下記の条件で社会保険料も含めた金額でシミュレーションを行っていきます。
個人の場合は国民健康保険+国民年金、法人の場合は厚生年金保険+健康保険=社会保険となり、社会保険料は個人負担と同額程度の法人負担が生じます。
年間所得が800万円の場合 → 所得控除は基礎控除48万円のみ考慮(配偶者なし、扶養なし)
-
個人事業主:全額事業所得
所得税111万円、住民税64万円、事業税25万円、国民健康保険(京都市)97万円、国民年金21万円
→合計:約318万円の負担
-
法人:役員報酬600万円、法人利益200万円-社会保険90万円=110万円
所得税22万円、住民税32万円、法人税31万円、社会保険料(本人負担)90万円+(会社負担)90万円
→合計:約265万円の負担
.
上記のパターンで法人成りした場合は
👉 年間約53万円の節税効果 となります。
.
法人化すれば
-
役員報酬による給与所得控除 を利用可能
-
退職金制度 を導入して将来の節税準備も可能
-
家族への給与支給 による所得分散も実現
- その他費用計上の幅が広がる
単純な税率の違いにとどまらず、幅広い節税策を活用できるのが法人化の大きなメリットです。
サイン② 取引先から法人化を求められたとき
次に注目すべきは「信用力」です。
大手企業や官公庁、金融機関との取引では、法人格を持っていることが必須条件となるケースが少なくありません。
法人化で得られる信用力の向上
-
銀行融資が受けやすくなる
-
大手企業や自治体との取引機会が増える
-
継続的な事業と認識される
-
採用活動で応募者が集まりやすくなる
個人事業主では参加できない入札案件も、法人であれば応募可能になります。
👉 信用力の向上による売上増加効果は、節税効果以上の価値 を持つ場合も少なくありません。
特に「法人化していただければ取引可能です」と言われたら、それは法人化を検討すべきサインです。
サイン③ 従業員を雇用する予定があるとき
従業員を雇用し始めると、社会保険や労務管理の面で法人化のメリットが顕著になります。
法人化のメリット(雇用面)
-
社会保険加入により 優秀な人材を確保 しやすくなる
-
労働保険の適用が明確になり、トラブル防止につながる
-
給与体系を整備しやすくなる
-
労務管理の信頼性が高まる
個人事業主のまま従業員を雇うと、社会保険の扱いが複雑になり、労務トラブルのリスクも増します。
特に 常時5人以上の従業員を雇用予定 の場合は、個人事業であっても社会保険の加入義務が発生してしまうため、法人化を強く検討すべきタイミングです。
法人化にかかるコストと注意点
法人化にはメリットが多い一方、デメリットやコストも存在します。
-
株式会社設立費用:約25万円(合同会社なら約10万円〜)
-
法人住民税(均等割):毎年7万円〜
-
社会保険料の会社負担分が増加
- 税理士などの専門家費用
つまり、年間で最低でも十数万円の維持コストが発生します。
そのため、節税効果や信用力向上、雇用メリットなどの 総合的なメリットがコストを上回るか を判断することが重要です。
まとめ:法人化を検討すべき3つのサイン
ここまでを整理すると、個人事業主が法人化を検討すべきタイミングは以下の3つです。
-
年間所得が800万円を超えた
→ 税率の違いで大幅な節税が可能 -
取引先から法人格を求められた
→ 信用力が増し、取引・売上の拡大につながる -
従業員を雇用する予定がある
→ 労務管理や社会保険制度がスムーズに整備できる
法人化の判断で迷ったら?
法人化は単なる節税だけでなく、事業拡大や人材確保にも直結する大きな経営判断です。
「いつ法人化すべきか」は事業の成長スピードやライフプランによっても変わるため、個別の状況に応じたシミュレーションが欠かせません。
👉 税理士に相談することで、法人化のメリット・デメリットを数値で比較 でき、最適なタイミングを見極められますので、お悩みの方はまずはご相談ください。