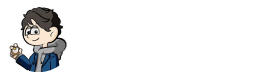― 京都の最低賃金が1,122円に ―
こんにちは!税理士の佐藤です。
今回は、経営者の皆さんにとって気になる話題、最低賃金引き上げについてお話しします。
2025年10月1日から順次、最低賃金が引き上げられ、京都府は11月21日から現行の1,058円→1,122円に引き上げられます。
時給64円のアップは、2002年度以降で最大の引き上げ幅となっています。
「たった64円でしょ?」と思われるかもしれませんが、従業員数が多い企業にとっては、この小さな数字が大きなインパクトを与えます。
本記事では、従業員(正社員)50人規模の会社を例に、具体的な人件費増加額や必要な売上増、そして実践的な対応策を、税理士の視点からわかりやすく解説していきます。
経営の数字が苦手な方も大丈夫です!
一緒に計算しながら、この変化をチャンスに変える方法を見つけていきましょう。
64円時給アップ額
(過去最大)
京都府は11/21適用開始日
(2025年)
614万円
50人企業の年間負担増
最低賃金引き上げによる人件費増加の試算
まずは、具体的にどれくらいの負担増になるのか、一緒に計算してみましょう。
1人あたりの増加分
📋 計算してみましょう!
最低賃金で働く従業員(正社員)1人あたりの影響を見てみます。
時給64円のアップ × 月160時間勤務(週40時間×4週) = 10,240円/月
年間では約12.3万円/人の増加
「月1万円ちょっとか…」と思うかもしれませんが、これは1人分の話。
従業員数が増えると、この金額は倍々で増えていきます。
正社員50人規模の会社の場合
🏢 50人企業の影響額
では、従業員(正社員)50人全員が最低賃金で働いている場合を想定してみましょう。
512,000円
約614万円
🚨 月間で50万円超、年間で600万円以上の負担増!
これは中小企業にとって無視できない金額ですよね。
もちろん、全従業員が最低賃金というケースは稀ですが、最低賃金近辺で働く従業員が多い業種(サービス業など)では、このような計算が現実的になってきます。
原価率別に見る「必要な売上増」シミュレーション
人件費が増えた分、どこかで補填する必要があります。
多くの場合、粗利(売上から原価を引いた金額)から補うことになります。
ここで重要なのが「粗利率」の考え方です。
粗利率は「1 − 原価率」で計算されます。
原価率が高い業種ほど、売上増で人件費増をカバーするのが大変になるんです。
ケース別シミュレーション
年間614万円の人件費増をカバーするために必要な売上増を、原価率別に見てみましょう。
💹 原価率別 必要売上増
(約68.3万円/月)
(約73.1万円/月)
(約78.8万円/月)
👉 この差は「業態による原価率の違い」で大きく変わるため、自社の数値で試算することが重要です。
例えば、コンサルティング業など原価率の低い業種と、製造業など原価率の高い業種では、必要な売上増が大きく異なってきます。
また、アルバイトが多いのか、正社員が多いのかなどの雇用形態によっても異なります。
給与アップによる社会保険料の追加負担も忘れずに
実は、最低賃金引き上げの影響は給与だけにとどまりません。
給与が上がると社会保険料も連動して上がるため、企業の実際の負担はさらに大きくなります。
📊 社会保険料の仕組み
社会保険料は労使折半のため、従業員の給与アップに伴い、企業側も追加で社会保険料を負担することになります。
健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を合わせると、給与増加額の約15%程度の追加負担が発生します。
💰 実際の負担増計算
人件費増を吸収するために企業が考えるべきこと
さて、ここからが本題です。
この人件費増をどう吸収するか、具体的な対策を見ていきましょう。
①シフト・労働時間の見直し
⏰ 働き方の効率化
- 残業時間の削減:割増賃金がかかる残業を減らし、正規時間内での生産性向上を目指す
- ピークタイム集中シフト:忙しい時間帯に人員を集中配置し、暇な時間帯の人件費を削減
- 非効率的な業務のカット:「なんとなく続けている作業」を見直し、本当に必要な業務に集中
②生産性向上
🚀 ITツールの活用
- 勤怠管理システムの導入:タイムカード集計の手間を削減
- 会計ソフトの活用:経理業務の自動化で事務コストを削減
- 予約・受注システムの導入:電話対応時間を減らし、コア業務に集中
- 作業マニュアルの整備:新人教育コストの削減と作業品質の均一化
③価格転嫁
💡 賢い値上げ戦略
- 単純な値上げだけでなく、メニュー改定やサービス料の導入を検討
- 付加価値の向上:なぜその価格なのかを顧客に納得してもらえる理由作り
- 段階的な価格改定:一気に大幅値上げするより、小刻みな調整で顧客の理解を得る
④雇用形態の最適化
👥 人員配置の見直し
- アルバイトと社員のバランス調整:業務内容に応じた適切な人員配置
- 社会保険加入ラインを踏まえた人員配置:週20時間以上勤務者の社会保険負担を考慮したシフト設計
- 業務委託などの外注化:部分的に外注することを検討
賃上げ税制の活用で負担軽減を図ろう
実は、国も企業の賃上げを支援する制度を用意しています。
「賃上げ促進税制」を活用すれば、人件費増の一部を税額控除として取り戻すことができます。
🎯 中小企業向け賃上げ促進税制のポイント
💰 節税効果の計算例
例えば、年間614万円の給与増があった場合、2.5%以上の増加要件を満たせば
614万円 × 30% = 約184万円の税額控除
これは大きな負担軽減になります!
⚠️ 重要な注意点
税額控除の上限は法人税、所得税の20%となります。
ただし、一定規模以下の事業者については、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能です。
詳細な適用可否については、必ず税理士にご相談ください。
最低賃金以外で見直すべき経費
人件費以外の部分でも、コスト削減の余地がないか点検してみましょう。
🔍 福利厚生や各種手当の逆転現象チェック
最低賃金が上がると、既存従業員との給与バランスが崩れることがあります。
- 勤続年数の長いパート従業員と新人の時給が逆転していないか
- 各種手当(皆勤手当、職務手当など)とのバランスは適切か
- 正社員の基本給との差が縮まりすぎていないか
💸 固定費の見直し
- 家賃の交渉:長期契約更新時の賃料減額交渉
- 仕入先との価格交渉:取引条件の見直しや新規仕入先の開拓
- 光熱費の削減:電力会社の見直しや省エネ設備への投資
🎁 補助金・助成金の活用
国や自治体では、中小企業の負担軽減のための支援制度を用意しています。
- 業務改善助成金:設備投資により生産性向上と賃上げを行う企業への助成
- IT導入補助金:業務効率化のためのITツール導入支援
- 省力化投資補助金:人手不足解消のための設備投資支援
具体的な数値例で理解を深めよう
実際の企業例で考えてみましょう。飲食店を経営するAさんの会社(従業員50人、うち20人が最低賃金近辺の正社員)の場合
🍽️ Aさんの飲食店の試算例
原価率35%(粗利率65%)の場合
282万円 ÷ 0.65 = 約433万円/年(約36万円/月)
📝 結論
つまり、Aさんは月間約36万円の売上増を実現しないと、今までと同じ利益を維持できないということになります。
※上記は正社員のみのシミュレーションですが、その他、アルバイト・パートについても賃上げが必要です。
賃上げを成長のチャンスに変える発想
ここまで「負担増」の話をしてきましたが、見方を変えれば、これは経営改善の絶好のチャンスでもあります。
😊 従業員満足度の向上
- 適正な賃金水準により、優秀な人材の確保・定着が期待できる
- 離職率低下により、採用・教育コストが削減される
- モチベーション向上により、生産性や接客品質が向上する
🌟 ブランド価値の向上
- 「働きやすい会社」として評判が上がり、求人応募数が増加
- 社会的責任を果たす企業として、顧客からの信頼も向上
- 取引先からの評価アップにより、新たなビジネスチャンスが創出
業務改善助成金の活用事例
政府は中小企業の負担軽減のため、様々な支援制度を用意しています。
特に注目したいのが「業務改善助成金」です。
🏆 業務改善助成金の概要
生産性向上のための設備投資を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる企業に対して、設備投資費用の一部を助成する制度です。
💰 助成金活用例
200万円のIT設備投資 → 最大160万円の助成
実質的な投資負担を軽減しながら生産性を向上できます。
今すぐできる経営者のアクションプラン
📋 具体的な行動計画をチェックしてみてください
- 自社の時給レンジと最低賃金を比較し、影響を受ける従業員数を把握する
- 人件費増の影響額を具体的に試算する(社会保険料増も含めて)
- 自社の原価率をもとに必要売上増を算定する
- シフト・業務改善の具体案を作成し、実行スケジュールを立てる
- 値上げ戦略と顧客への説明方法を検討する
- 賃上げ促進税制の適用可能性を税理士と相談する
- 補助金・助成金の活用可否を専門家と検討する
よくある質問と回答
Q: 最低賃金引き上げを機に、正社員の給与も上げる必要がありますか?
A: 法的義務はありませんが、社内バランスを考えると調整が必要な場合が多いです。
最低賃金で働くパート従業員と正社員の給与差が縮まりすぎると、正社員のモチベーション低下につながる可能性があります。
Q: 賃上げ促進税制は必ず適用できますか?
A: 一定の要件を満たす必要があります。
前年度比での給与増加率や、青色申告の実施などが条件となります。
詳細は税理士にご相談いただくのが確実です。
Q: 価格転嫁が難しい業界では、どう対応すればよいですか?
A: 生産性向上と業務効率化に重点を置きましょう。
IT導入補助金や業務改善助成金を活用して、少ない人数でも同じ成果を出せる体制作りが重要です。
まとめ
最低賃金引き上げは、従業員が多い会社にとって数百万円規模のコスト増となります。
原価率に応じて必要売上増は異なりますが、いずれにせよ大きな負担となることは間違いありません。
ただし、これは単なる負担ではなく、経営改善の絶好のチャンスでもあります。
この機会に業務の見直し、IT化の推進、従業員満足度の向上など、長期的な企業価値向上に取り組むことで、より強い企業体質を作ることができるでしょう。
🎯 成功の3ステップ
「試算 → 対策 → 実行」
賃上げ促進税制や各種助成金の活用も含めて、数字に基づいた戦略を立てることが成功のカギです。
一人で悩まず、税理士や社労士など専門家に相談しながら、この変化を乗り切り、さらなる成長につなげていきましょう!
※本記事の内容は2025年8月時点の情報に基づいています。
最新の制度内容については、関係機関にご確認ください。