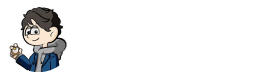飲食店の経営者からよく聞くのが、「売上は目標以上に出ているのに、なぜか手元にお金が残らない」という悩みです。頑張って売上を上げているのに資金繰りが厳しい。これは非常につらい状況ですが、実は多くの店舗が共通して陥っている問題でもあります。本記事では、その原因と解決策を5つの視点から解説します。
1. 「売上=利益」ではないという現実
まず大前提として、売上が伸びていても利益が残らないことは十分にあり得ます。
売上というのはあくまで“表面的な数字”であり、実際に経営において重要なのは利益=売上-経費です。売上に気を取られて経費の管理が疎かになると、「売上はあるのに苦しい」という状態に陥ってしまうのです。
飲食店では、特に原価と人件費が全体の経費の大半を占めます。これらを適切にコントロールしない限り、いくら売上が伸びても手元にお金が残らない構造になってしまいます。
2. 原価率と人件費率を「数値」で把握しよう
利益を残すために、まず注目すべきなのが「原価率」と「人件費率」の2つの指標です。
-
原価率(=食材費 ÷ 売上) → 目安:28~35%
-
人件費率(=人件費 ÷ 売上) → 目安:30%以下
この2つを足した**FL比率(Food+Labor)**が60%以内であれば、その他の経費を差し引いても黒字が見込めます。
この数字を定期的に把握するだけで、「食材の無駄な仕入れ」や「人件費のかけ過ぎ」に気づくことができ、自然と経営が改善の方向へ向かっていきます。
3. 数字を見て行動するだけで利益は変わる
実際に私の支援先でも、「毎月FL比率を見ながら改善点を洗い出す」ことを習慣にしただけで、利益率が大きく向上した店舗が数多くあります。
例えば、原価率が毎月35%を超えていた居酒屋では、「仕入れ先の見直し」「高原価メニューの見直し」「廃棄ロス削減」などを実施。たった2ヶ月で原価率が32%まで改善し、利益増につながりました。
数値を見ることで、「どこに手を打つべきか」がはっきりと見えてくるのです。
4. 現場でできる具体的な改善アクション
数字の意識と並行して、実際のオペレーションを見直すことも重要です。
例えば
-
仕入れの頻度を週3回に分ける
→ 鮮度維持・ロス削減・過剰在庫の防止に効果的 -
アルバイトのシフトを売上予測に合わせて調整
→ 無駄な人件費を抑えながら、混雑時のパフォーマンスも維持 -
定番メニューの原価再計算
→ 利益率の低いメニューを見直すことで全体収益を底上げ
こうした取り組みは一つ一つは地味ですが、積み重ねることで確実に利益体質の店舗へと変わっていきます。
5. 感覚経営から数字経営へシフトする
「なんとなくこのくらいでいいだろう」といった感覚頼みの経営から、「数値に基づいた経営」へと切り替えることが、飲食店の利益改善には不可欠です。
数字を見るのは苦手…という方も多いですが、最低限「売上・原価・人件費」だけでも月次でチェックする習慣をつけるだけで、驚くほど意思決定が変わります。
また、会計ソフトや経営ダッシュボード(例:マネーフォワード・マネージボード)を活用すれば、複雑な経理知識がなくても簡単に数値の可視化が可能です。
まとめ|「数字で見る経営」が利益を残すカギ
飲食店経営は、料理の味やサービスだけでは成り立ちません。
日々の仕入れや人件費を管理し、数字を見ながら経営判断をすることで、初めて「売上が利益につながる」店舗運営が実現します。
「売上はあるのにお金が残らない」と感じたら、まずは原価率と人件費率をチェックすることから始めてみてください。それが、利益を残すための第一歩です。