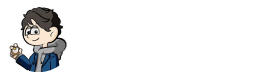「利益は出ているのに、税金で手元に残らない…」
そんな悩みを抱える小規模事業者や個人事業主は少なくありません。実は、正しい知識を持ち、制度を活用するだけで 年間数十万円の節税 が可能です。
本記事では、税理士が厳選した 小規模事業者(個人事業者・法人向け)の節税術6選 を分かりやすく解説します。
👉 本記事を読むとわかること
-
小規模事業者が取り入れるべき節税方法
-
個人事業主でもすぐに使える控除・経費計上のポイント
-
法人限定で効果が大きい節税スキーム
節税術① 小規模企業共済で退職金を準備しながら節税(個人)
個人事業者や法人役員のための「退職金制度」として活用できるのが 小規模企業共済 です。
-
毎月1,000円〜70,000円を積み立て可能
-
掛金は全額「所得控除」対象
-
契約者貸付で資金繰り改善にも活用できる
例えば月額5万円を積み立てると年間60万円が控除に。税率20%の場合、約12万円の節税効果 が期待できます。
共済金は退職・廃業時に受け取れますが、退職所得になるため税負担は抑えられます。
なお、任意解約も可能ですが、その場合は退職等のタイミングに比べると解約返戻金の額は減り、税負担は重くなります。
契約者貸付制度は金利1.5%(R7.8月時点)となり、金融機関で融資を受けるよりも低金利です。
借入可能額は積み立ててから1年以上経過した金額の7~8割程度が可能で、返済期間は6ヵ月、12か月、24か月、36ヵ月、60か月から状況により選択します。
24か月以上の場合は6ヵ月ごとの返済となりますが、6ヵ月と12か月の場合は期限に一括返済となります。(返済時は同額借換も可能)
節税術② 経営セーフティ共済でリスク対応+節税
取引先倒産のリスクに備えながら節税できるのが 経営セーフティ共済(倒産防止共済)。
-
掛金は「全額損金算入」可能
-
年間最大240万円まで拠出できる
-
契約者貸付で資金繰り改善にも活用できる
「保険的機能」と「節税効果」を兼ね備えた仕組みです。
解約後2年間は再加入の損金算入ができないため、計画的な活用が必要です。
こちらも小規模企業共済と同様に契約者貸付制度が利用できます。
ただ、借入期間は1年間のみなので、毎年借換の手続きを行う必要があります。
節税術③ 少額減価償却資産の特例を活用する
通常なら数年かけて減価償却する資産でも、30万円未満なら即時償却 できます。
-
年間上限は合計300万円まで
-
対象例:パソコン、プリンター、事務机、椅子、エアコン、軽自動車など
期末直前の設備投資にも有効で、その年の利益調整に直結します。
なお、少額減価償却資産は償却資産(事業用の資産には税金がかかります)に含まれるため、要件を満たす場合は3年で均等償却する一括償却資産(10万円以上20万円未満)として処理することも検討が必要なのでご注意ください。
一括償却資産として処理すれば償却資産からは除外されます。
節税術④ 家事関連費の適切な按分(個人事業主向け)
自宅兼事務所を使っている個人事業主は、家賃・光熱費・通信費などを事業割合で経費計上 できます。
-
家賃:事務所利用30%なら30%を経費に
-
車両費:業務利用70%なら70%を経費に
-
通信費:事業利用50%なら50%を経費に
按分割合は合理的な方法で見積もり、根拠を明確に記録しておくことが重要です。
例えば、自宅兼事務所の場合などは、家賃や通信費などを事務所スペースの広さ(㎡)で按分するのが合理的です。
節税術⑤ 出張旅費規程の活用(法人限定)
法人であれば、役員・従業員への出張日当を非課税で支給 できます。
【日当例】
-
日帰り出張:3,000円
-
宿泊出張:5,000円
-
海外出張:10,000円
給与課税ではなく経費処理できるため、社会保険料の負担軽減にも効果的です。
出張が日常的にあるのであれば、整備しておきたい規程です。
ただし、役員のみに支給している場合は給与に該当する可能性があるため、役員・従業員(役職)などでそれぞれ支給する金額を規定する必要があるのでご注意ください。
節税術⑥ 社宅制度の活用(法人限定)
法人が役員の自宅を「社宅」として借り上げることで、法人側は費用計上でき、役員側は家賃負担を抑えられる 仕組みです。
家賃月額20万円の場合
-
会社負担:約192〜216万円を費用計上可能/年間
-
役員負担:約48~24万円を負担/年間
ただし、豪華すぎる社宅は税務調査で否認リスクがあるため注意。
小規模な社宅(132㎡以下)の場合は下記の計算式で役員の家賃負担額を算出します。
次の(1)から(3)までの合計額
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
※上記金額を計算する際は、市役所などで固定資産税の評価明細などを取得する必要がありますが、賃貸契約書の控えなどがあれば賃借人でも取得できますので、必要資料などを市役所などに問い合わせてから資料を準備しましょう。
まとめ:小規模事業者が押さえるべき節税の鉄板6選
最後に、今回の節税方法を整理します。
-
小規模企業共済 → 退職金+所得控除(最大46万円節税)
-
経営セーフティ共済 → 倒産リスク備え+損金算入(最大240万円)
-
少額減価償却資産の特例 → 30万円未満の資産を一括経費化
-
家事関連費の按分 → 自宅・車・通信費を適正に経費化
-
出張旅費規程(法人) → 非課税日当で節税
-
社宅制度(法人) → 住居費を実質経費化
上記の制度を活用し、できることから少しずつ進めていきましょう!