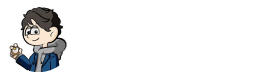「損益計算書って、経理の人が見るものでしょ?」
そう思っている飲食店経営者の方は要注意です。
実は、損益計算書(P/L:Profit and Loss Statement)は、売上があっても利益が残らない原因を数字で“見える化”するための最も重要なものです。
今回は、飲食店経営における損益計算書の役割と見方、活用方法を5つの視点からわかりやすく解説します。
1. 損益計算書とは?なぜ飲食店に必要なのか
損益計算書とは、一定期間の経営成績を示すレポートです。
「いくら売上があったのか」「どのくらいのコストがかかっているのか」「最終的にいくら利益が残っているのか」を把握するために欠かせません。
飲食店では、食材費や人件費、水道光熱費、家賃など、日々さまざまな経費がかかります。
損益計算書を定期的にチェックすることで、感覚ではなく数字で経営の健康状態を判断できるようになります。
特に「売上はあるのにお金が残らない」という悩みは、P/Lを見れば原因がはっきりすることが多いです。
2. 飲食店が見るべき損益計算書の主要項目
損益計算書には多くの項目がありますが、飲食店経営者がまず注目すべきは以下の3つです。
● 売上総利益(粗利)
売上から売上原価(食材費)を引いた金額です。
粗利は、店舗が経費を払う前に持っている「利益のタネ」です。
● 営業利益
粗利から人件費・家賃・光熱費・広告費などの販売費および一般管理費を差し引いた金額。
営業活動によって生み出された本当の利益で、飲食店では営業利益率10%以上が理想とされています。
● 経常利益・当期純利益
金融機関との付き合いや税引き後の最終的な利益を確認するための指標。ここまで見られればさらに安心です。
3. 損益計算書はどうやって作る?
損益計算書の作成方法は大きく2つあります。
✅ Excelなどで自作
日々の売上・仕入・人件費・固定費を入力すれば、独自の損益管理表が作れます。自分で構造を理解するには有効ですが、手間がかかりやすいのが難点です。
✅ 会計ソフトを使う
マネーフォワードやfreeeなどのクラウド会計ソフトを使えば、早期に損益計算書を作成することができます。
POSレジや銀行口座と連携すれば、売上や入出金が自動で反映されるので、より正確かつ効率的に数字を管理できます。
4. P/Lから何がわかる?FL比率のチェックも重要
損益計算書の情報を活用すれば、経営の改善ポイントが見えてきます。
中でも特に注目したいのが**FL比率(Food & Labor)**です。
これは、売上に対する食材原価と人件費の合計割合を示す指標で、飲食店経営では非常に重要です。
-
原価率の目安:28〜35%
-
人件費率の目安:30%以下
-
FL比率の目安:60%以内
FL比率が高すぎる場合は、仕入れの見直し・メニュー構成の工夫・シフトの最適化などが必要です。
損益計算書でこの指標を毎月チェックすることで、赤字リスクを未然に防ぐことができます。
5. 経営の意思決定は「数字」で行う時代
「最近忙しいけど、あまり儲かってる気がしない」
「なんとなく売れてる感じはあるけど、実際の利益がわからない」
そんな不安を感じている方こそ、損益計算書を経営判断の基礎として使うべきです。
損益計算書を見る習慣ができると、
✅ 経費の使いすぎに早く気づける
✅ 粗利の悪いメニューを発見できる
✅ 今後の投資判断(改装・増員など)に迷わなくなる
つまり、数字に基づいて「攻める」か「守る」かを選べる経営者になれるのです。
まとめ|損益計算書は“現場の味方”になるツール
損益計算書は、単なる経理書類ではなく、飲食店経営者にとっての経営ナビです。
お金の流れを「感覚」ではなく「数値」で捉えることで、無理なく利益体質へと変えていくことができます。
会計ソフトやPOSとの連携で数字管理はますます簡単になっています。
「ちょっと見てみようかな」と思ったら、それが第一歩です。
損益計算書を活用する経営で、店舗をより強く、健全に育てていきましょう。